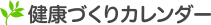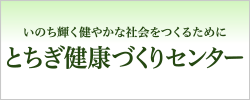日本人は糖尿病になりやすいのか、糖尿病はどんな病気か
欧米人に比べ、日本人は、生活習慣病に起因する2型糖尿病になりやすい体質(遺伝的素因)を持っていると言われています。そこに、食べ過ぎや運動不足による肥満が加わり、糖尿病になる人が急激に増えています。糖尿病の有病者数は全国では約552万人、栃木県で約10万7千人(令和5年患者調査)と推定されています。
糖尿病にかかりやすいかどうかチェックしてみましょう。
※チェックが多いほど、糖尿病にかかりやすいので注意が必要です。
|
□肥満気味である |
□お酒をたくさん飲む
|
栃木県民の生活習慣の状況
|
肥満が多い (肥満者の割合) |
野菜の摂取量が足りない (1日の摂取量の平均) |
|
1日の歩数が足りない (1日の歩数の平均) (20~64歳) 男性 8,000歩以上 女性 7,000歩以上 (65歳以上) 男性6,000歩以上 女性 6,000歩以上 |
健診を受けている人が少ない 特定健康診査実施率60.8% ☆目標は70%! ※令和5年度 厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況」 |
※上記目標値はとちぎ健康21プラン(3期計画)目標値
糖尿病はどんな病気ですか?
血液中の糖(ブドウ糖)を「血糖」といい、私たちの体には血糖値を一定に保つ働きがあります。糖尿病はその仕組みが崩れて、血糖値が常に高い状態になる病気です。早い時期には、症状がほとんどないため、悪い状態になってから気づくことが多い病気です。
糖尿病を予防するにはどうしたらよいでしょうか?
次の2つが重要です。
1.肥満改善と体重管理 BMI(肥満指数)を参考に体重管理を。
《BMI(肥満指数)の計算式》
BMI(肥満指数)=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
※普通体重の場合18.5以上25.0未満
《標準体重の計算式》
標準体重=身長(m)×身長(m)×22
標準体重を目指しましょう
| 肥満改善と体重管理のポイントは2つ | |
|
■普段の食事に気をつけましょう |
■積極的に体を動かしましょう。 |
2.年に1回は健診受診
特定健康診査(いわゆる「メタボ健診」)や定期健康診断(いわゆる「事業者健診」)で糖尿病の検査(血糖値やHbA1cなど)を受けましょう。
血糖値が「高い」「少し高め」と言われたら、「まだ大丈夫」とそのままにせず、必ず医療機関を受診するようにしましょう。
【栃木県糖尿病重症化予防プログラムの活用】
栃木県糖尿病重症化予防プログラムは、県内の保険者が糖尿病重症化予防のため医療機関と連携しながら被保険者の皆さんへ、情報提供、受診勧奨、保健指導を行います。
プログラムは県ホームページに掲載しております。
糖尿病を治療しないでおくとどんな影響が出るでしょうか?
高血糖状態が続くと、体中の血管がダメージを受けて動脈硬化が進行し、血管が詰まりやすくなったりします。それによる様々な合併症が起こります。
| 細い血管の障害 | |
| 糖尿病網膜症 | 視力が弱まります。初期には自覚症状が少ないため、ある日突然目が見なくなって気づくこともあります。 |
| 歯周病 | 糖尿病ではない人に比べ、歯周病になる危険度は約3倍。 |
| 糖尿病腎症 |
体の中の老廃物をろ過する機能が低下します。自覚症状がほとんどないため、知らない間に進行し透析に至る場合もみられます。 |
| 糖尿病神経障害 | 手足の神経に障害が起こり、痛みやしびれを感じるようになります。 |
| 糖尿病足病変 | 糖尿病神経障害の悪化から痛みを感じにくくなり、火傷やけがをしても気づかず、壊疽(えそ)による切断に至る場合もあります。 |
| 太い血管の障害 | |
| 脳梗塞 |
糖尿病ではない人に比べ、脳梗塞を起こす危険度は2~4倍高い。 |
| 心血管疾患(心筋梗塞) | 糖尿病ではない人に比べ、心筋梗塞を起こす危険度は3倍以上。 |
糖尿病を重症化させないためにはどうしたらよいでしょうか?
血糖値が高くならないよう、コントロールしていくことが重要です。
もし、糖尿病と診断されたら
●食事や運動の指導を受け、適正な食生活や運動の実践、禁煙を心がけましょう。
●定期的医療機関を受診し、血糖値などをチェックし、一定の血糖値を保つよう、血糖コントロールを行いましょう(眼科や歯科も定期的に受診し、合併症を予防しましょう)。
糖尿病と糖尿病合併症に関するデータ
・糖尿病網膜症による失明者 全国年間3,000人以上(新規失明者の約18%)
・糖尿病足病変による足切断者 全国年間3,000人以上(全切断患者の40~50%)
・糖尿病腎症による新規透析導入患者 全国年間13,000人以上(新規透析導入患者の約38%)
・R5年栃木県の糖尿病腎症による新規透析導入患者 年間272人(新規透析導入患者の約46%)
・R5年栃木県の透析患者数6,717人 うち糖尿病腎症が原因である患者の割合は約40%
糖尿病治療を担う県内の医療機関
栃木県では、糖尿病の治療を行う医療機関の機能分担と連携を進めるため、「糖尿病の初期・安定期治療」「専門治療」「急性合併症治療」「慢性合併症(糖尿病網膜症・糖尿病腎症・糖尿病神経症)治療」の要件を定め、各々の治療を行う医療機関について情報提供を行っています。詳しい内容は下記栃木県のホームページよりご覧ください。
世界糖尿病デーとブルーサークル
11月14日は世界糖尿病デーです。世界に広がる糖尿病の脅威に対応するため、国連により制定されました。
青い丸をモチーフにした「ブルーサークル」は、空の「ブルー」と団結を表す「輪」をデザインした、糖尿病啓発キャンペーンのシンボルマークです。
栃木県では、世界糖尿病デーが制定されている11月を、糖尿病予防・重症化防止強化月間として、市町村や団体、企業、医療機関と連携し、重点的に糖尿病の予防や治療継続の重要性についての啓発を行っています。